【64才メンタルケアスペシャリストでトレー二ー歴7年の私がお伝えします😊お悩み相談も承ります😊👌】

はじめに:なぜ「ぐるぐる思考」は心を疲れさせるのか?
🧠「ぐるぐる思考」とは何か?
「ぐるぐる思考」とは、同じことを何度も繰り返し頭の中で考えてしまう、いわゆる**“反すう思考”**のことです。
たとえば──
「なんであんなこと言っちゃったんだろう」
「相手はどう思ったかな…」
「ちゃんと伝わってない気がする…」
こんなふうに、一度終わった出来事やまだ起きていない未来のことを、エンドレスに考え続けてしまう状態。
この反すう思考は、もともと脳が「問題を解決しよう」としているサインでもあります。
けれど、放っておくと思考が深みにはまり、不安やストレスを増幅させ、心のエネルギーを消耗させてしまいます。
結果として──
- 集中力が下がる
- 気持ちが沈む
- 人間関係に距離を感じる
- 夜、眠れなくなる
といった、日常生活にも深刻な影響を及ぼすこともあるのです。
でも大丈夫。
「ぐるぐる思考」は、ちょっとした習慣の工夫で、必ず変えていくことができます。
このあとは、思考を整え、心を軽くする具体的な方法をご紹介していきます。
小さな一歩から、一緒に始めていきましょう🌱
ここからは、そんな思考を整え、心を軽くする具体的な習慣を紹介していきます。
第1章:マインドフルネスと瞑想で思考を整える
「マインドフルネス」とは、過去や未来のことではなく、“今この瞬間”に意識を向ける生き方のことです。
例えば、呼吸に意識を向けるだけでも、頭の中のノイズが少しずつ静かになっていきます。
ティム・フェリス氏など、数々の実業家が実践している瞑想習慣は、集中力を高めるだけでなく、不安を鎮める効果があることで知られています。
🧘♀️ はじめてのマインドフルネス呼吸法(1日3分)
- 静かな場所に座り、背筋をやさしく伸ばす
- 目を閉じても、軽く開けていてもOK
- 鼻からゆっくり息を吸って、口からゆっくり吐く
- 「吸う」「吐く」に意識を向ける(思考が浮かんでもOK。その都度、呼吸に戻す)
- 3分間だけでも続けてみる
「マインドフルネス」は、うまくやることではなく、“気づき直すこと”の練習です。
うまく集中できなくても大丈夫。「気が散った」と気づいて戻る、その繰り返しが大切です。
第2章:認知行動療法(CBT)で思考パターンを変える
反すう思考を断ち切るためには、まず自分の思考に気づくことが第一歩です。
「どうして自分はこんなに考え込んでしまうのか?」という問いに答えるために、役立つのが**認知行動療法(CBT)**の手法です。
🧠「反すう焦点化認知行動療法」とは?
これは、ネガティブな思考ループに入ってしまうクセを、以下の3つのモードに変える練習を通して整理していく方法です。
✍️ 1. 具体モード(Concrete)
→ 今できること、具体的な事実に意識を向ける
例:「どうしよう…」→「まずは一つだけ片づけてみよう」
🧩 2. 没頭モード(Engagement)
→ 何かに集中している時間を増やす(運動・読書・料理など)
🤲 3. コンパッションモード(Compassion)
→ 自分にやさしい言葉をかける習慣
例:「また考えすぎてる。でもそれって、頑張ってる証拠だよね」
📝 思考記録表で思考のクセを“見える化”しよう
以下のようなフォーマットで書き出すと、自分のパターンに気づけます。
| 出来事 | そのときの考え | 感じた感情 | とった行動 | 今できること |
|---|---|---|---|---|
| 会議で発言できなかった | 嫌われたかも… | 不安、後悔 | 1人で反省して落ち込んだ | 次はメモを用意しておこう |
たった数行でもOK。書き出すことで、思考のループから少し距離を置くことができます。
💡 まとめ
思考を変えるには、「気づく→書き出す→切り替える」という3ステップが有効です。
完璧を目指す必要はありません。まずは1日1つ、書いてみることから始めましょう。
第3章:身体活動と習慣で心をリセットする
「ぐるぐる思考」にハマってしまったとき、
それを止めようと頭の中で必死になるよりも、体を動かすことの方がリセット効果が高い場合があります。
🏃♀️運動は、脳に効く「心のストレッチ」
軽く外を歩くだけでも、呼吸が整い、景色が変わることで思考のループが自然に緩んでいきます。
散歩・ストレッチ・ヨガ・ダンスなど、好きな運動を5分だけでも取り入れるのがおすすめです。
💡運動は、ストレスを減らすホルモン「セロトニン」や「エンドルフィン」の分泌も促します。
✨「気晴らしリスト」を作っておこう
いざというときに手軽に気分を切り替えるためには、あらかじめ「気晴らしの選択肢」を用意しておくことが効果的です。
🔖 例:あなたの“気晴らしリスト”
- お気に入りの音楽を1曲だけ聴く
- コーヒーをゆっくり淹れる
- 軽くストレッチする
- 小さな観葉植物に水をあげる
- 写真を見返す/好きな香りをかぐ
- 無言で外の空を見る など…
※「スクロールするSNS」より、五感を使う行動がおすすめです。
🌱「ちょっとだけ」が大切
「全部やらなきゃ」と思うと、かえってストレスになります。
大事なのは、「ぐるぐるし始めたな」と気づいた瞬間に、ほんの少し別の行動を入れること。
“動くことで切り替える”クセをつけていきましょう。
📌まとめ
- 運動は思考のリセットボタン
- 気晴らしリストは“ぐるぐる予防ツール”
- 日常に“心をほどく習慣”を持とう
💤 第4章:睡眠と脳の関係を理解する

「寝ても疲れが取れない…」
そんなときは、“体”ではなく“脳”が疲れているサインかもしれません。
🧠 脳は「考えすぎ」でも疲れる
何もしていないように見える「ぼーっとしている時間」でも、脳内では「デフォルトモードネットワーク(DMN)」という領域が活発に働いています。
このDMNは、以下のようなときに活性化します:
- 反すう思考(ぐるぐる考え続ける)
- 過去の出来事を思い返しているとき
- 不安や後悔にとらわれているとき
つまり、「何もしていないつもり」でも、脳はずっと“考え疲れ”をしている状態なのです。
🛏 睡眠は“思考のクリーンアップ”タイム
睡眠中、脳は次のような作業をしています:
- 情報の整理・記憶の定着
- 情緒の調整
- 神経の修復とメンテナンス
この時間がしっかり確保されないと、翌朝も頭が重く、思考がネガティブに傾きやすくなります。
🌙 良質な睡眠を取るための習慣
🕒 就寝1〜2時間前はスマホを手放す
💡 部屋を間接照明に切り替えて、光をやわらかく
📖 ベッドに入る前に、軽くストレッチや読書で心を静める
📔「今日考えていること」をノートに書き出してから眠る
💡 特に、寝る前のぐるぐる思考は「ノートに預けておく」と脳が休みやすくなります。
✨まとめ
- 脳も“考えすぎ”で疲れる
- DMNの暴走を防ぐには、睡眠とリラックスが重要
- 良質な睡眠=ぐるぐる思考リセットの第一歩
🌿 第5章:HSP(Highly Sensitive Person)のための思考整理術

HSP(Highly Sensitive Person)は、生まれつき感受性が高く、周囲の刺激や感情に敏感に反応します。
このため、日常のちょっとした出来事も深く受け取りやすく、「ぐるぐる思考」に陥りやすい傾向があります。
🧠 なぜHSPはぐるぐる思考しやすいの?
- 相手の表情や声のトーンに敏感で、気にしすぎてしまう
- ひとつの出来事を深く分析し、「こうすればよかった」と何度も思い返す
- 自分よりも他人を優先しがちで、後から自分を責めてしまう
だからこそ、心の整理とケアの時間を意識的に取ることがとても重要なのです。
✍️ おすすめ①:書いて整理する「ジャーナリング習慣」
ぐるぐるした思考は、頭の中だけで考えているとループし続けます。
でも、ノートに書き出すことで、それを客観視し、手放す準備ができます。
📓 ジャーナリングの書き方(例)
- 「今日、心に引っかかったことは?」
- 「そのとき、どんな気持ちだった?」
- 「本当はどうしたかった?」
- 「今、自分にかけてあげたい言葉は?」
1日5分でもOK。書くことで、自分とやさしく対話ができます。
💬 おすすめ②:「私は大丈夫」と思えるアファメーション
HSPは周囲の声に影響されやすい反面、自分自身の声(セルフトーク)にも強く反応します。
だからこそ、「自分を認める言葉=アファメーション」は心の支えになります。
🌸 アファメーション例:
- 「私は、私のままで大丈夫」
- 「私は感じやすいけれど、それは強みです」
- 「私は価値ある存在です」
- 「私は、安心して自分を表現していい」
朝や寝る前、鏡の前などにそっと唱えてみましょう。
書いてもOKです。少しずつ、心の中に優しい軸が育っていきます。
✨まとめ
- HSPは、深く考える分、疲れやすくもある
- 書くこと&肯定的な言葉で、思考を整えられる
- 「私はこれでいい」と思える習慣を身につけよう
📱 第6章:SNSとの付き合い方を見直す

SNSは便利で楽しいものですが、同時に「情報過多」や「他人との比較」を生み出しやすく、心を疲れさせてしまうことがあります。
❗ SNSが「ぐるぐる思考」の引き金になる理由
- 他人の“キラキラ投稿”を見て、つい比べて落ち込む
- コメントや既読に反応して、「どう思われてるんだろう」と不安になる
- 気づけば無意識にスクロールし続けて、思考もまとまらなくなる
こうして、気づかないうちに**「情報に飲まれる状態」**になってしまうのです。
🌿 まずは試してみよう:「SNS断ち習慣」
“完全にやめる”必要はありません。
まずは、小さなところから“距離を取る”ことを始めてみましょう。
💡 今日からできる簡単ステップ:
- 📵 通知をオフにする(急ぎの用事は別手段でOK)
- ⏱️ SNSを見る時間帯を決める(例:朝食後だけ/昼休みの10分だけ)
- 📲 アプリを1つだけログアウトする/ホーム画面から外す
- 📓 SNSの代わりに「今の気持ちを書く」習慣を1日5分取り入れる
💬 こんな声もあります:
「朝SNSを開かずに10分静かにコーヒーを飲む時間をつくったら、それだけで心が軽くなった気がします」
「“通知を切っただけ”でも、頭の中が静かになって、考えが整理しやすくなりました」
✨まとめ
- SNSは、無意識に心のノイズを増やすことがある
- 小さなSNS断ちで、頭と心に“空白”が生まれる
- 自分のペースを取り戻すための「距離の取り方」を選ぼう
💛 第7章:自己肯定感を育むための習慣

私たちはつい、「ちゃんとやらなきゃ」「もっと頑張らなきゃ」と、完璧を求めてしまいがちです。
でも実は、**「完璧じゃなくていい」**という考え方こそが、心を軽くする大きな鍵。
🍃「80%でOK」が心を守ってくれる
- 「100点を目指さなくていい」
- 「失敗しても大丈夫」
- 「がんばりすぎない自分でも、ちゃんと価値がある」
この“80%マインド”を持つだけで、心に余裕が生まれ、行動にも柔らかさが出てきます。
🌼 小さな「できた」を見つける習慣を
自己肯定感は、何かを達成してから得るものではなく、日々の小さな積み重ねで育つものです。
🌟 例:こんなことも立派な「成功体験」
- 朝、時間通りに起きられた
- 忙しい中でも深呼吸できた
- 「ありがとう」が言えた
- 自分にとって苦手なことに少しだけ挑戦できた
\大事なのは、“意識して自分を認める”こと/
たとえそれが「当たり前のこと」でも、「できたね、私」と声をかけてあげましょう。
✍️ おすすめワーク:「今日の小さな達成3つ」
1日1回、「今日できたこと」を3つだけ書き出してみましょう。
どんなに小さなことでも構いません。
続けることで、**「私にはできていることがある」**という感覚が自然と育ちます。
💬 アファメーションの例:
- 「私は、がんばりすぎなくても大丈夫」
- 「私は十分に価値のある存在です」
- 「私は少しずつ、前に進んでいます」
✨まとめ
- 完璧を目指すより、「今の自分にOKを出す」ことが自己肯定感の第一歩
- 小さな「できた」に気づくことが、心の土台になる
- 「がんばる」より、「気づいて認める」習慣を持とう
🌈 第8章:ネガティブ思考からポジティブ思考への転換

ネガティブな思考は、決して“悪いこと”ではありません。
私たちの脳には、危険を避けたり、自分を守ったりするために、ネガティブに考える本能があるのです。
でも、それに長く支配されすぎてしまうと、心は疲れてしまいます。
🔄 まずは、「ネガティブになってる自分」に気づこう
- 「どうせうまくいかない」
- 「あのときこうすればよかった」
- 「また同じ失敗をするかも…」
そんな言葉が浮かんできたとき、「あ、今ちょっとネガティブモードかも」と気づくだけでもOK。
そこから、ほんの少し視点を変えてみましょう。
✨ ステップ①:「今、できること」に目を向ける
ネガティブ思考は「過去」や「まだ来ていない未来」に意識が向いている状態。
だからこそ、“今できる小さなこと”に意識を戻すことが効果的です。
💡 例:
- とりあえずお茶を淹れる
- 3分だけ外の空気を吸う
- 1つだけタスクに手をつけてみる
→ 小さな行動が、“今ここ”の感覚を取り戻してくれます。
✍️ ステップ②:「できたことリスト」を書いてみる
どんなにネガティブな気持ちでも、「今日できたこと」を書き出すだけで、自分への見方が少しずつ変わっていきます。
例:「今日の小さなできたこと」
- 朝ちゃんと起きた
- 返信1件できた
- 自分に優しい言葉をかけた
- コンビニでレジの人に「ありがとう」が言えた
→ 小さな達成感が、自分に対する“信頼感”を育ててくれます。
💬 自分へのひとことも添えてみよう
- 「よくやったね」
- 「疲れてても頑張ってた」
- 「今日はこれで十分!」
このような小さな声かけが、心を整えてくれます。
✨まとめ
- ネガティブな思考は自然なもの。でも、そこに居続けなくていい
- 小さな「今できること」「今日できたこと」に目を向けよう
- 自分に“やさしくする練習”が、前向きな気持ちへの第一歩
🧩 第9章:ストレス対処法としての「コーピングリスト」

「ストレスがたまってるな…」と感じたとき、
無理に我慢したり、感情を押し込めたりすると、“ぐるぐる思考”が暴走する引き金になります。
そんなときに役立つのが――
✨「コーピング」=自分に合ったストレス対処法
「コーピング」とは、ストレスを感じたときに、自分の心を落ち着けたり回復させるための行動や工夫のことです。
大切なのは、「誰かにとって正しい方法」ではなく、**“自分にとってラクになれること”**を知っておくこと。
💡 どうしてコーピングが大切なの?
私たちは日々、仕事・人間関係・情報など、さまざまなストレスにさらされています。
ストレス自体はなくせなくても、**「それにどう対処するか」**は選ぶことができます。
そして、「ぐるぐる思考」に陥っているときこそ、**“行動”で思考のループを断つ”**ことが有効なのです。
🧘♀️ すぐできる!コーピングの例
以下は、誰でもすぐに試せる「気晴らし」や「自分を整える行動」です:
- 好きな香りをかぐ(アロマ・ハンドクリーム)
- お気に入りの飲み物をゆっくり飲む
- 体を伸ばして深呼吸
- 静かな音楽を聴く/自然音に耳をすます
- 「今の気持ち」をノートに書いてみる
- 10秒間だけ空を見上げてみる
- 好きな言葉やアファメーションを唱える(例:「私は落ち着いている」)
📝「コーピングリスト」を作ってみよう
コーピングは“ひとつ”ではなく、“たくさんの引き出し”を持っておくと、もっと心強いものになります。
あなた自身の「私に効くコーピング」を、ぜひリスト化してみてください。
📓 書き出すときのヒント:
- 時間がないときにもできることは?
- 気分転換になることは?
- ちょっとほっとできる習慣は?
- 逆に、あまり効かない対処法は?
🌱 まとめ
- コーピングとは「ストレスとやさしくつきあう技術」
- 自分にとっての「小さな癒し」を知ることが大事
- あなたの“こころの引き出し”を増やしていこう
🔄 第10章:思考の整理と行動習慣の見直し
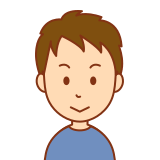
私たちの思考や感情は、日々の行動によって大きく影響を受けています。
ネガティブ思考を変えようとするのは簡単ではありませんが、
行動を変えることなら、今日からすぐに始めることができます。
💡「行動」が変わると「思考」も変わる理由
- 朝の行動 → その日一日の気分を左右する
- SNSの使い方 → 情報に振り回される or 自分の時間を大事にできる
- 夜の振り返り → 過去を責める or 成長を確認する時間になる
行動が少し変わると、考え方のクセも自然に変わっていくのです。
🌅 1. 「朝のルーティン」で心の準備を整える
朝、ほんの5分でいいので、自分と向き合う時間をつくってみましょう。
例:
- 深呼吸 or 軽いストレッチをする
- 「今日大切にしたい気持ち」をノートに書く
- ポジティブな言葉(アファメーション)を1つ唱える
→ 「私は、今日も落ち着いて過ごします」
📱 2. SNS時間を“管理”ではなく“デザイン”する
SNSを見る時間・見ない時間を「区切る」ことで、心が静かになります。
例:
- 朝はスマホを見ない(30分だけでも)
- 通知をオフにする
- 夜の○時以降はアプリを閉じる
→ 「思考を整える“余白時間”」が増えていきます。
🌙 3. 1日の終わりに「小さな振り返り」をする
ネガティブな反省会ではなく、「よかったこと・できたこと・感じたこと」を記録する時間を持ちましょう。
書くときのヒント:
- 今日よかったことは?
- 自分をほめたいポイントは?
- 明日、意識したいことは?
→ 自己肯定感がじわじわ育っていきます🌱
✨まとめ
“自分の時間”を意識的にデザインしよう
思考を変えるより、行動を変える方が現実的でやさしい
「小さな習慣」が積み重なると、心の土台がしっかりしてくる
🌸 おわりに:ぐるぐる思考から自由になるために
ぐるぐる思考は、誰にでもある“こころの習性”です。
でも、それに巻き込まれすぎず、自分らしく心地よく過ごすためには、日々の小さな意識と行動の積み重ねが何より大切です。
深呼吸をする
気晴らしをしてみる
「今日できたこと」をひとつ見つける
それだけでも、心は少しずつほぐれていきます。
どうか、あなたの心が少しでも軽くなるように。
今日からできることを、ひとつずつ、あなたのペースで始めてみてくださいね。
焦らなくて大丈夫。
心は、ちゃんと応えてくれます🍀

最後まで読んでいただきましてありがとうございます。少しでも読者様の幸せに貢献できれば幸いです。
ご意見、ご感想をコメント欄に寄せていただければ励みになります。
お悩み相談も承ります。

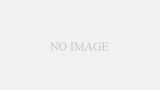
コメント
Perfectly indited written content, regards for selective information.
コメントありがとうございます。
これからもよろしくお願いします。
Your place is valueble for me. Thanks!…
Woah! I’m really enjoying the template/theme of this site. It’s simple, yet effective. A lot of times it’s hard to get that “perfect balance” between superb usability and appearance. I must say you’ve done a awesome job with this. Also, the blog loads extremely quick for me on Firefox. Outstanding Blog!
こんにちは。
コメントありがとうございます。
私のサイトを楽しんでいただけて光栄です。
これからもよろしくお願いします。
感謝
you have a great blog here! would you like to make some invite posts on my blog?
You are my breathing in, I own few blogs and rarely run out from to post : (.
I am not rattling fantastic with English but I get hold this really easygoing to understand.
Thank you for sharing excellent informations. Your site is so cool. I’m impressed by the details that you have on this web site. It reveals how nicely you understand this subject. Bookmarked this web page, will come back for extra articles. You, my friend, ROCK! I found simply the information I already searched all over the place and just could not come across. What a great site.
こんにちは!
元気になるコメントありがとうございます。
これからもこのサイトを楽しんで下さいね。
感謝
I’m really inspired with your writing skills as smartly as with the layout to your weblog. Is this a paid theme or did you modify it your self? Anyway keep up the excellent high quality writing, it is uncommon to look a nice weblog like this one today..
嬉しいコメントありがとうございます。
これからもこのサイトを楽しんで下さいね。
感謝
You can definitely see your skills within the work you write. The arena hopes for even more passionate writers like you who aren’t afraid to say how they believe. All the time go after your heart. “Golf and sex are about the only things you can enjoy without being good at.” by Jimmy Demaret.